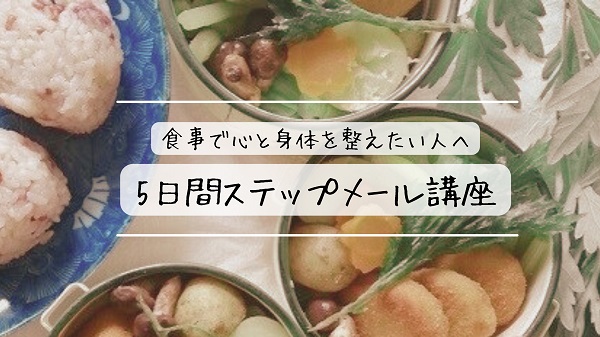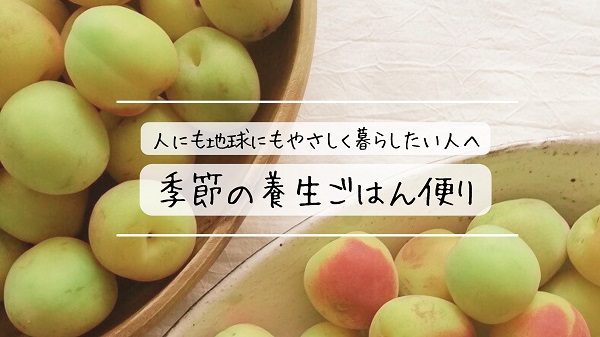郷土料理の現状・課題とは|「衰退」ではなく食文化を守るために
「郷土料理ってどんなもの?」「郷土料理の魅力とは」では、全国各地にある個性豊かな郷土料理と共に、人にも環境にもやさしい魅力を紹介しました。
では、郷土料理は現在どのような状況にあり、どんな課題を抱えているのでしょうか。今回は、郷土料理の現状と課題について考えてみたいと思います。
〇この記事を書いた人…薬膳と郷土料理の研究家:松橋かなこ

↑ 無料メールマガジン(週1~2回配信)をご希望の方はこちらからご登録をお願いします。
郷土料理の現状|「受け継いでいない」が3割超

農林水産省サイトに掲載されている「食育に関する意識調査報告書(令和3年3月)」によれば、郷土料理や伝統料理など、地域や家庭で受け継がれてきた料理や味、箸づかいなどの食べ方・作法を受け継いでいるか聞いたところ、「受け継いでいる」と回答した人の割合が65.9%、「受け継いでいない」と回答した人の割合が34.0%となっています。
特に、20~39歳までの若い世代では「受け継いでいない」という人が約4割を占めていて、全年代の平均を上回っています。また、男性と女性を比較すると、「受け継いでいない」という人は男性のほうが多いという結果でした。
なぜ郷土料理が衰退しているのか?
郷土料理が衰退しつつある主な理由として、まず食生活の変化が挙げられます。もう少し具体的に説明すると、食のグローバル化が進み日本食を食べる機会が少なくなっていることや、家庭で調理する機会が少なくなっていることなどです。
顕著な例として、魚を使った料理をする人が少なくなっています。その結果として魚の消費量は下降傾向にあり、魚を使った郷土食を食べる機会も減りつつあります。
また、核家族化や地域とのつながりの希薄化なども、郷土料理が衰退する大きな要因になっています。このほか、一昔前に比べて郷土料理に使われる食材が手に入りにくくなっていることも挙げられます。静岡県の「うなぎのかば焼き」や愛知県の「ひつまぶし」などのように、うなぎの価格高騰により、郷土料理がいわゆる「高級料理」になってしまったケースもあります。
郷土料理や伝統食の魅力を伝える取材記事を制作
養生ふうどでは、日本に古くから伝わる郷土料理や伝統食の魅力を次の世代に伝えるべく、作り手に取材・インタビューを行い記事を制作しています。
こちらは、日本文化の入り口マガジン「和樂web」(運営:小学館)に掲載中の昆布会社への取材記事です。
地道な取り組みかもしれませんが、こうした取材記事の積み重ねによって食文化を守り、伝えていきたいと考えています。
郷土料理や食文化を残し伝えていくために

先に紹介した「食育に関する意識調査報告書(令和3年3月)」では、 郷土料理や伝統料理など、地域や家庭で受け継がれてきた料理や味、箸づかいなどの食べ方・作法を受け継ぐために必要なことについても調査しています。
その結果は「親等から家庭で教わること」を挙げた人の割合が92.4%と最も高く、次いで、「子どもの頃に学校で教わること」(41.6%)、「ふだん食べているもののうち、どれが郷土料理や伝統料理か知る機会を増やすこと」(40.9%)の順でした(複数回答、上位3項目)。
また、 食文化を受け継ぐために必要なことについて聞いたところ、若い世代(20~39歳)では「子どもの頃に学校で教わること」「食に関するイベント等で教わること」を挙げた人の割合が高くなりました。

↑ 昔ながらの郷土料理や食養生について、メルマガからも配信しています(週1~2回配信)。

ここからわかることは、家庭や学校など身近な環境において、郷土料理について学ぶ機会を設けることが大切なのではないかということです。
郷土料理や食文化を学ぶことは、その地域のことをより深く知るだけでなく、自然への恵みに感謝する「やさしい気持ち」を育てることにもつながります。また、できるだけ早い時期から学ぶことで、知識ベースではなく感覚的に理解することができるでしょう。
今回は、郷土料理の現状と課題についてお伝えしました。これをきっかけに、郷土料理を残し伝えていくために自分にできることは何かを一緒に考えてみませんか。
●養生ふうどでは「養生ごはん教室」や「我が家のごはん史」を通して、郷土料理や地域の食文化を伝える活動を行っています。また、取材・プロモーション支援にも柔軟に対応しています。ブログの感想やご相談は、こちらからお気軽にご連絡ください。
●養生ふうどでは「食事で心と身体を整えたい」「人にも地球にもやさしく暮らしたい」という人に向けて、「ステップメール講座(無料)」と「養生ごはん便り(メルマガ)」を配信しています。ぜひご活用ください^^
外部リンク