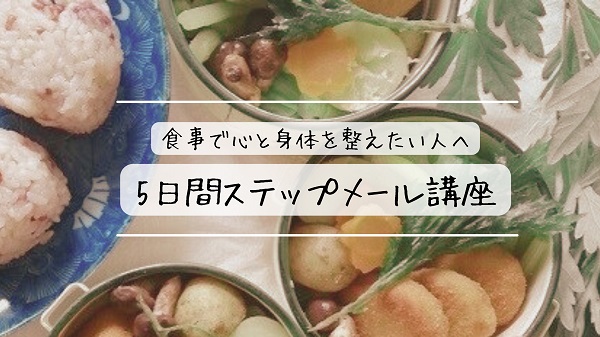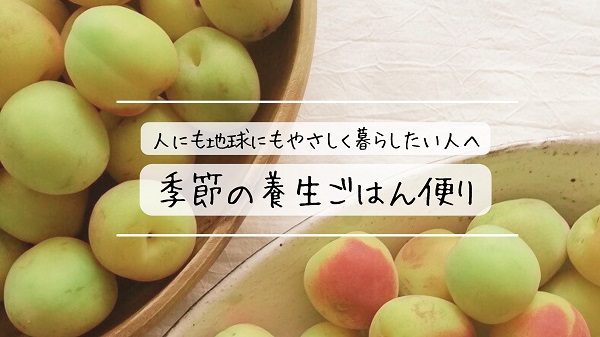捨てないで。むくみ予防にもぴったりの「冬瓜の皮茶」の作り方・レシピ
冬瓜は、みずみずしくて料理に幅広く利用できる野菜です。冬瓜という漢字から「冬野菜」と思っている人もいるようですが、実は、立派な夏野菜です。
薬膳では、冬瓜は利尿作用が期待できる食材で、むくみ予防にもよく使われています。特に、皮は実の部分よりも利尿作用が高いとされていて、捨ててしまうのはモッタイナイ!
そこで今回は、冬瓜の皮の効能と、冬瓜の皮を使ったお茶の作り方・レシピを紹介します。
●この記事を書いた人……薬膳と郷土料理の研究家 松橋かなこ

↑ 無料メールマガジン(週1~2回配信)をご希望の方はこちらからご登録をお願いします。
冬瓜の皮は食べられる?|薬膳では利尿作用が高くむくみ予防にも

冬瓜は、実だけでなく、皮やわたも丸ごと食べることができます。
皮は別名「冬瓜皮(とうがんひ)」と呼ばれ、生薬としても用いられます。実の部分よりも高い利尿作用があるとされています。
ちなみに、中国や台湾では「冬瓜茶」という飲み物があります。冬瓜と砂糖を一緒に煮たもので、身体の熱を取る働きや解毒作用が期待されています。
冬瓜は淡泊な味わいなので「栄養がなさそう」というイメージを持つ人もいるかもしれません。しかし実際には、口当たりが良くて、夏の不調対策にもぴったりの健康野菜です。
冬瓜の皮は硬い?まずい?
冬瓜の皮は硬さがあるので、生ではなく加熱するのがおすすめです。冬瓜の皮を千切りにして、きんぴらなどにすると比較的食べやすいです。
我が家では、ヘタの部分は苦味は強いことが多いので、ヘタの部分だけは避けるようにしています。
それでも食べにくい場合は、下茹でしたものを千切りにして使うようにしてみましょう。ハーブやスパイス、カレー粉など、香りのよい食材と一緒に調味するのもおすすめです。
冬瓜の皮はどこまでむく?

冬瓜の断面には「導管」と呼ばれる小さな穴が空いています。その穴を目印にして厚さ5~7mmを目安にむくようにしましょう。
冬瓜の皮は包丁かピーラーでむきます。滑りやすいので、手を切らないように注意してください。
冬瓜の皮茶を作ってみよう

冬瓜の皮は料理に使って食べることができますが、独特の食感や苦みが気になる人もいるかもしれません。そんな人におすすめなのが「冬瓜の皮茶」です。
番茶などとブレンドしたり、生姜やスパイスを加えたりすると、とても飲みやすくなります。
材料(作りやすい分量)
・冬瓜の皮 ある分だけ
作り方
1.冬瓜の皮をむく。

2.冬瓜の皮を適度な大きさにカットして、ザルに並べて天日で干す。

3.カラカラに乾いたら天日干しは完了。キッチンはさみなどで細かく切る(このままでもOKですが、厚手のフライパンなどで乾煎りしておくと、香ばしい風味のお茶になります)。

飲み方
お湯を注ぐだけだと味が出にくいので、5~10分程度弱火で煮出してください。分量の目安は、一人分につき冬瓜の皮が大さじ1杯程度です。
ほかのお茶やスパイスなどとブレンドする場合は、冬瓜の皮の量を調整してくださいね。
干し野菜への想いはこちらから
ドライフルーツや干し野菜づくりをライフワークとしてお伝えしています。これまでの活動と想いについてはこちらをご覧ください。
冬瓜の皮茶で、人にも地球にもやさしい暮らしを始めよう

冬瓜の皮は普段捨ててしまいがちな部分ですが、乾燥させてお茶にすれば、むくみやすい身体にぴったりのお茶になります。
薬膳では、捨ててしまいがちな部分に驚くべき効能があるケースも多く、今回の冬瓜の皮もそのひとつです。
「人にやさしい」と「地球にやさしい」は深くつながっているーー。これは、とても素晴らしいことですよね。
そんな食の知恵をこれからもお伝えしていきたいと思います。それでは、また。
●養生ふうどでは「食事で心と身体を整えたい」「人にも地球にもやさしく暮らしたい」という人に向けて、「メール講座」と「養生ごはん便り(メルマガ)」を配信しています。ぜひご活用ください^^
養生ふうどでは、「養生ごはん教室(対面・オンライン)」や「我が家のごはん史づくり」などの活動を行っています。ご質問・ご相談がありましたら、お問合せフォームからお気軽にご連絡ください。